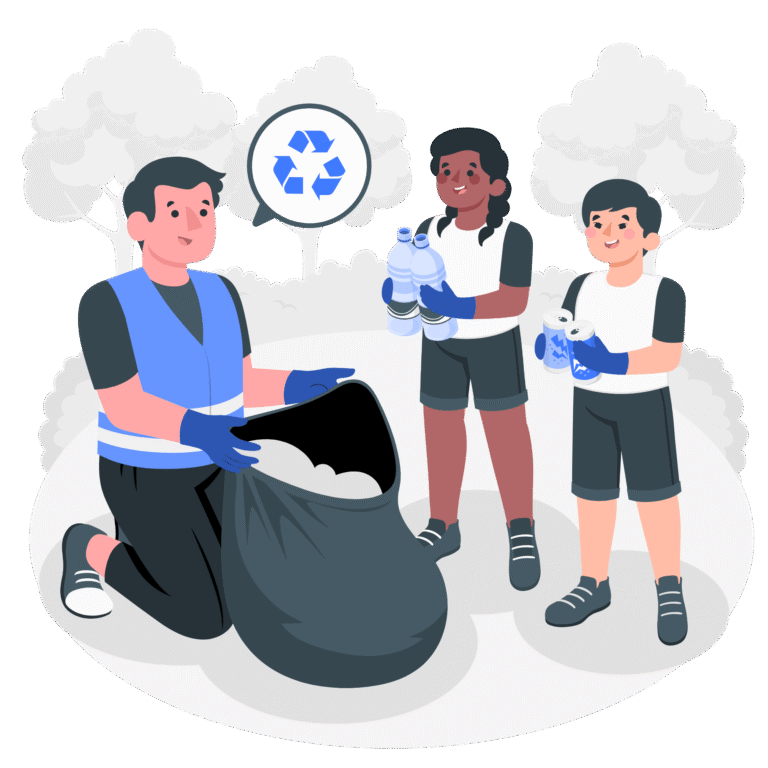皆さんが分別したプラごみ、本当にリサイクルされていると思いますか?
私たちは日々の生活の中で、「これはプラごみだから資源になる」と思って、しっかり分別して捨てていますよね。でも実は、その多くが“リサイクルされず”に焼却されたり、埋め立て処理されたりしている現実をご存じでしょうか?
「再生プラスチック」は、環境問題への希望として注目を集めていますが、その裏側には多くの課題や誤解もあります。
今回は、私たちが日常的に関わる「プラスチックのリサイクル」について、正しい知識と最新の動向をわかりやすく解説します。
再生プラスチックとは?仕組みと現状
「再生プラスチック」とは
再生プラスチックとは、使用済みプラスチックを回収・処理して再び原料として利用するリサイクル素材のこと。
代表的なのはペットボトルから作る再生PET(rPET)で、衣類や容器などに生まれ変わっています。
一方で、お弁当の容器やレジ袋、カップ麺のフタなど、リサイクルが難しいプラごみも数多く存在しています。
日本の「リサイクル率」は高い?カラクリを解説
日本ではプラスチックの「リサイクル率」が約85%とされていますが、実はその多くが「サーマルリサイクル(焼却による熱回収)」です。
これを“リサイクル”と呼ぶかどうかは、国際的にも意見が分かれています。
つまり、「資源として再利用」される再生プラスチックの割合は、私たちが思っているよりもずっと少ないのです。
これ捨てても大丈夫?再生できる・できないプラの見分け方
再生できないプラごみの例
- 汚れた容器(油やソースがついた弁当容器など)
- 多層構造のパッケージ(銀色のスナック袋など)
- 色付き・黒いプラスチック(リサイクル選別機が誤作動を起こす)
見た目が「プラ」でも、リサイクル不可能なものが多くあるのです。
プラマークの落とし穴
「プラ」マークが付いていても、それが「リサイクルできる」ことを意味するわけではありません。
これはあくまで材質を示すマーク。「素材+清潔さ+自治体ルール」の三拍子がそろわなければ、リサイクルには回らないのです。
再生プラスチックが活躍する現場
再生材で作られた製品たち
- ユニクロの再生ポリエステルを使用した服
- 文房具メーカーの再生プラ使用商品(クリアファイルやボールペン)
- 家具や車の部品にも使われる再生素材
環境に配慮した商品として、企業も再生プラの活用を加速させています。
ケミカルリサイクルの進化
最近注目されているのが、「ケミカルリサイクル」。
これはプラスチックを科学的に分解し、元の原料まで戻す技術。色付きや汚れたプラスチックでも対応可能で、今後の技術革新が期待されています。
私たちにできる、身近なエコアクション
「再生プラ製品を選ぶ」ことが第一歩
商品を買うとき、「再生素材を使っているか?」をチェックするクセをつけてみましょう。
環境配慮型マーク(例:GPNマーク、エコマークなど)を参考にするのもおすすめです。
捨てない工夫で“脱プラ生活”
- マイボトル・マイバッグを常備
- 詰め替え用の商品を選ぶ
- 繰り返し使える保存容器に切り替える
「プラスチックを使わない」よりも、「使い捨てない」ことが重要です。
まとめ:そのごみ、本当に“ただのごみ”ですか?
「再生プラスチック」は、確かに未来への希望ですが、それを活かせるかどうかは私たち次第です。
大切なのは、“分別すること”ではなく、“その先を考えること”。
今日からできるアクションとして、
- 汚れたプラは洗って出す
- 再生プラ製品を意識して選ぶ
- 「使い捨てない」選択をする
この3つを意識して、日々の暮らしから“持続可能”を実現していきましょう。