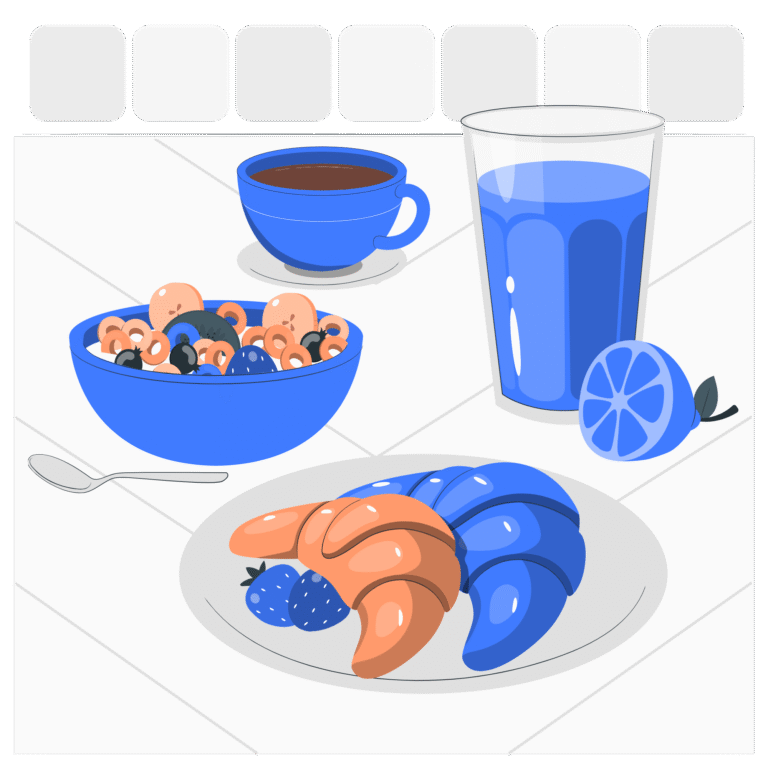「ごみ」が“食べ物”になるってどういうこと?
「プラスチックからパンが作れる時代が来るかも」――そんな話を聞いたら、びっくりするのではないでしょうか?
ペットボトルのようなプラスチックごみが、微生物の力によって分解されて、なんと“パンの材料”や“燃料”、“香料”にまで生まれ変わるというのです。
一見、信じがたいこの話。実は、イギリスのケント大学とポーツマス大学で本格的に研究が進められている最先端のバイオ技術なのです。
酵母って、ただのパン作りの微生物じゃない!
「酵母(イースト)」と聞くと、パンやビールを思い浮かべる人が多いでしょう。確かに、酵母は糖を食べてアルコールや炭酸ガスを出す、パン作りや発酵食品に欠かせない存在です。
でも最近では、それだけではありません。
酵母は**「生きた化学工場」**として、私たちの暮らしを支えるさまざまな物質を作るために利用されています。たとえば:
- 薬の原料
- 香料やフレグランス
- バイオ燃料(ガソリンの代わりになるもの)
- プラスチックの代替になるバイオ素材 など
つまり、酵母は私たちの未来を支える“働き者の微生物”なのです。
でも…酵母が食べるエサが高すぎる?
酵母がものを作るには、エネルギー源、つまり「エサ」が必要です。これまではグルコース(ブドウ糖)という糖が主に使われています。
ところがこのグルコース、実は結構高価です。さらに、グルコースは人間の食料とも競合するため、「環境に優しい」とは言いにくい側面もあります。
そこで注目されているのが、「プラスチック」です。
プラスチックは世界中で大量に捨てられていて、その多くがリサイクルされずに埋め立てや焼却処分されています。
もしこれを酵母が“食べられる”ようになったら、廃棄物を有効活用する画期的な技術になりますよね。
プラスチックを分解できる酵素、ついに発見!
ここ数年、世界の研究者たちは「プラスチックを分解できる酵素(たんぱく質)」を発見しはじめました。中でも注目されているのが、ペットボトルに使われている「PET(ポリエチレンテレフタレート)」を分解できる酵素です。
この酵素を使うと、PETは「EG(エチレングリコール)」や「TPA(テレフタル酸)」という化合物に分解されます。
そして驚くべきことに、パン酵母がこのEGやTPAをエネルギー源として使えることが、実験でわかってきたのです。
つまり、酵母にとって「PETの分解物=エサ」になるのです!
ケント大学とポーツマス大学の挑戦
この夢のようなアイデアを現実にしようと、イギリスのケント大学とポーツマス大学では、以下のような研究が行われています。
- 酵母にプラスチック分解酵素を作らせる
酵母が体の外に酵素を出して、プラスチックを分解できるようにします。 - 酵素を酵母の表面にくっつける
酵母の“外側”に酵素を貼りつけることで、より効率よく分解が進む可能性があります。 - プラスチックごみを発酵タンクに入れる方法を研究
細かく砕いたプラスチックをどのように酵母のいる装置に入れるか、効率や安全性を考慮して工夫しています。 - 新しい酵素が発見されたらすぐに使えるようにする
世界中で発見されている新しい分解酵素を、酵母に導入できる体制を整えています。 - プラスチックの分解物が酵母の中でどう代謝されるかを調べる
分解された物質が酵母の代謝の中でどう使われるのかを追跡し、最適化を進めています。
ごみが“資源”になる社会へ
この研究が進めば、私たちの未来は大きく変わるかもしれません。
- プラスチックごみが、価値ある製品の「原料」に!
- 酵母が、香料・薬・バイオ燃料を安く作れるように!
- 廃棄物を循環させる「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の実現!
私たちが普段「いらない」と思って捨てているごみが、実は社会を支える“資源”になる。
科学の力でそんな未来がすぐそこまで来ているのです。
最後に
このような研究は、バイオテクノロジー、環境科学、化学、さらには情報科学など、さまざまな分野の知識が融合して成り立っています。